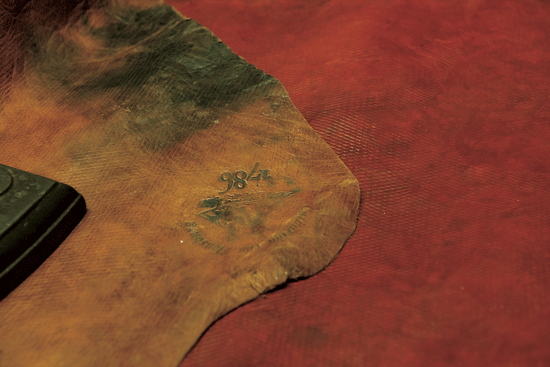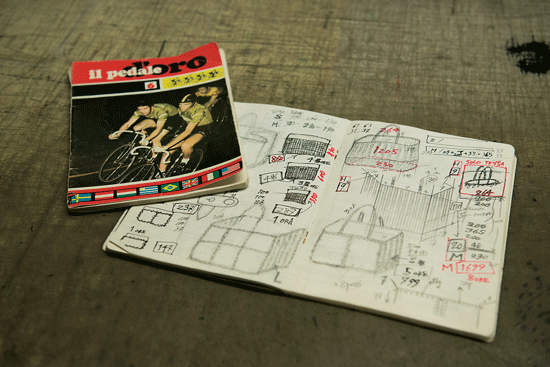フィレンツェという街を滋養に、靴や作品を生み出す職人・深谷秀隆氏。この職人は、彼というクラシックを生き、表現しているのかもしれない。深谷氏の店『イル・ミーチョ』に訪れ、クラフツマンのつくる靴や作品に触れる。

イタリア・フィレンツェに構える職人・深谷秀隆氏の店「イル・ミーチョ」における“ものづくり”
下の写真の靴は、2018年に限定販売された、「Hidetaka Fukaya per TOMORROWLAND」の、トゥモローランド40周年記念モデルのサンプル。この靴をデザインした深谷秀隆氏に導かれるまま、フィレンツェのマリノ・マリーニ美術館前にある像の足元で撮影してみた。経年による風化で石が削れ、セントバーナードの顔のようになったライオン像と、記念モデルのアッパーに表れた複雑な曲線が、妙にしっくりと、それぞれ「溶けて」いるように見える。

この「溶ける」イメージはまた、本取材に訪れた2018年よりさらに2年以上前に、ここマリノ・マリーニ美術館の中で見ることができた。深谷氏が手がけた、靴をモチーフにつくられたアート作品の展覧会。靴が有機的に、さまざまなフォルムにメタモルフォーゼしたような一連の作品の中に、文字どおり融解・液状化したようなフォルムの作品もあった。本来硬質な質感で、伝統を背負った「お堅い」存在でもある紳士靴が、ぐにゃりと溶けたような様子。クラシックの崩壊を表現したのか、といった邪推が掻き立てられる。
靴の撮影を終えて、歩いてすぐの深谷氏の店「イル・ミーチョ」に戻る途中、石畳の道の工事現場があった。路傍にはこれから道に敷くための石が積んであった。「500年前に道に敷いた石を掘り起こして、敷き直すんです。フィレンツェはどこもこんな感じですね。うちの店の前も3年前にこのリノベーションをやりました」
古いものが好きだから、囲まれていると気分が上がる。
深谷氏の言葉からはクラシックなものへの温かな視線が感じられた。先に触れた彼の作品は、クラシックへの反発というより、ライオン像がまさにそうだったように、古く朽ちていくものへの愛惜を、形にしたのかもしれない。古いものへの想い、思い起こすと、それは折に触れて彼の口から聞かされてきた。
今回の取材でもそんなシーンがあった。取材冒頭、深谷氏は店の奥にある「カバッロ(馬)」という器具に跨り手縫いの作業をしていた。その傍には古い木のボビンに巻かれたもはや使えなくなった糸や、数々の道具が置かれていた。
「このへんの道具には、100年以上経っているものもあります。古いものが好きだから、囲まれていると気分が上がる」そう、古くクラシックなもの、それが持つ何かは、空気や水同様に、彼という人間をここフィレンツェで「生かして」いるようだ。それに養われながら、彼は靴をつくり続け、さらにはアート作品という果実も生み出している。
深谷氏の創作意欲を触発するフィレンツェの文化
そんな深谷氏がこのフィレンツェにやってきたのは、1990年代の終盤。『フィレンツェ職人通り』(中嶋浩郎・著、NTT出版)という本に導かれるように渡伊したのだった。その本には若き日のステファノ・ベーメル氏が紹介されていた。深谷氏はベーメル氏のもとを訪ねるが、弟子入りは叶わなかった。いくつか工房を回ったのち、シエナのアレッサンドロ・ステッラという職人の元で働くことになった。しかしそこで行われていた靴づくりは、手仕事は多かったものの、深谷氏がイメージしていたハンドメイドの靴づくりとは違っていたという。
以前、彼は次のように話していた。「当時のイタリアの靴は、今と全くつくり方が違います。どちらかというと粗かった。細かなところだとベヴェルドウエストのつくり方が違うし、ヒールのつくりも違う。さらに当時そうしたことを教えてくれる人は周りに誰もいませんでした」
その後フィレンツェを本拠に自身の靴づくりを追求するなかで、深谷氏は英国やフランス、ハンガリーなど、ヨーロッパ各地を旅している。 各地で靴職人たちに会い、彼らの靴づくりを見てフィレンツェに戻り、自分で実際にやってみる。その繰り返しを経て、今の彼の靴づくりや靴の。スタイルが導かれたのだという。
そして2005年に現在の場所に靴店「イル・ミーチョ」を開店。その後はバッグやレザーグッズなども手がけ、トゥモローランドとの既製靴ブランド「Hidetaka Fukaya per TOMORROWLAND」を開始した。店の10周年を機に開催したのが先述したマリノ・マリーニ美術館での作品展。それは2017年に東京にも巡回し、大きな話題となった。
現在、工房では深谷氏のほか3人の職人がものづくりに携わっている。ひとりはバッグを製作する職人、2人が靴のメイキングなどを担当する 職人だ。靴のアッパーは外部のクローザーに依頼している。靴づくりに関わるメンバーは、深谷氏のアート作品の制作も行う。工房の中には進行中の作品がいくつか散見された。

あいつの仕事はしょうがない、と認められること。アートもまたクラシックの発露か。
「次の作品はより複雑な形状になります。クローザーの女性はどんなものを縫っているかわかっていないでしょうね」と深谷氏。ただ、その女性も先日の作品展を見て驚いていたというから、何に関わっているかは認識しているようだ。
「あいつの仕事はしょうがない、ってみんなに言われていますよ。この靴だってそうでしょう」そういって深谷氏が示したのは、冒頭で撮影した靴のアッパーの型紙。靴のパターンとは思えない曲線と非対称な形状に、当初メーカーの担当者は唖然としていたそう。
「でも、そのメーカーのトップも僕の作品展を見てくれて、すごく喜んでくれた。自分で言うのもなんです が、彼は 僕のことを認めてくれています。というか、認めてもらっていないと、イタリアでは一緒にものづくりはできないでしょう」クラフツマン同士ゆえの信頼関係が具体化した今回の靴。それはその見た目以上に、深谷氏の作品と繋がりがある。
「記念モデルとして、一回しかつくらないので、アート的でもいいと思ったのです。既製靴のコレクションは継続も考えられるので、通常こうしたアプローチはとりません」そのように説明する深谷氏に、つい聞かずにはいられなかった。イル・ミーチョのビスポーク、「Hidetaka Fukaya per TOMORROWLAND」の既製靴、そして作品。
それらの根底にある、深谷秀隆のものづくりのベースとは何か、そしてどのようなものを志向しているのか。「基本的には、クラシックですよ、あくまでも」そう言って深谷氏は、言葉を切った。その口吻からは、クラシックは自らの手の裡にあるとでもいうような、自負めいたものが感じられた。
il micio di Hidetaka Fukaya(イル ミーチョ/ヒデタカ フカヤ)
Via dei Federighi, 6, 50123 Firenze FI
tel:( +39)055 212295
photographs_Satoko Imazu
〇 雑誌『LAST』 issue.14 より