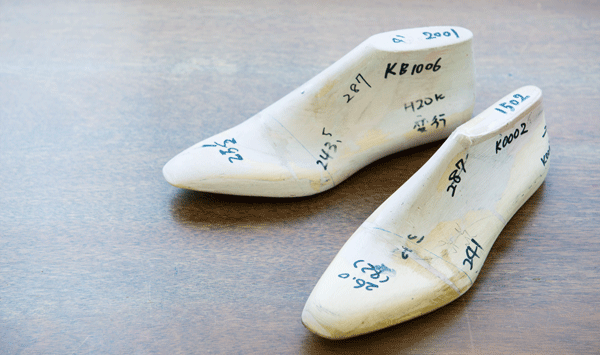ストイックなクラシシズムを感じさせる靴。それを実現しているのは、日本のクラフツマンシップだ。
現代のクラシックを実現する『カルマンソロジー』の技術とこだわり。デザイナーも動く、突き詰めたものづくり。
2018年の春からスタートしたシューズブランド『カルマンソロジー』。ブラックカラーのレザーを中心としたストイックなラインナップ、クラシックを基調としながらも新鮮さを感じさせる世界観など、さまざまな点でデビュー時から大きな話題を呼んだ。中でも、靴として実現されたデザインやディテールには、日本のファクトリーの高い技術が反映されていた。そこで今回、カルマンソロジーの靴を担うふたつのメーカーを訪ね、つくられた靴の背後にあるノウハウや思いを、デザイナーの金子真氏とともに探った。

世界長ユニオンのファクトリーへ訪問
『カルマンソロジー』のドレス系モデルを中心に手がける
まず訪れたのは、千葉・鎌ヶ谷にある世界長ユニオンのファクトリー。カルマンソロジーのドレス系モデルを中心に手がけている。最初に案内されたアッパーの縫製を行う部屋で、担当の櫻田亮一氏は 次のように語った。「金子さんの依頼は、アッパーのステッチピッチを、一寸(3センチ)で19針にしてほしいということでした。これまで17針はありましたが、19というのは初めてです。その都度現場で調整が必要でした」ミシンを調整し、試し縫い。メジャーをあてると確かに19針だった。金子氏も頷く。ステッチピッチだけでなく、アッパーのラインやパーツの重なりも複雑なため縫製には時間が必要で、一日2足分程度しか仕上がらないという。「こんな細かな作業は、彼らでないとできません」と金子氏。こうした繊細な作業はアッパーの縫製に止まらない。アッパーを木型につり込む作業は、トウラスターなどの機械ももちろん使うが、横づり(靴の両サイドをつり込む)は基本的に手作業で行う。「カルマンソロジーの木型は、いわゆるセンターがあいまいです。意図的にずらして内側に曲げています。そうした形状をうまく再現してくれていますね」(金子氏)
さらに本底を縫う出し縫いの工程で、ステッチピッチの課題がまた浮上する。「出し縫いを、一寸に10針入れないといけないところが大変でした。以前の機械だと縫っていて煙が出るくらい細かい。新しく機械を導入して、クリアしています」こう語る櫻田氏に、金子氏はすかさず「もうちょっと、11針は欲しい」と切り返した。その場で靴をチェックするとなんと10・5針。出し縫いは細かすぎると、ウェルトやソールの針穴と針穴の間が裂けてしまいがち。縫い進む方向と反対側に引っ張るようにしながら、早く行き過ぎないように縫っています、と現場の職人が語る。「現場としては確かに大変です。でも、きれいな靴、いい靴をつくっている感触はある。自社内の企画だとつい生産しやすい靴を考え、結果として平凡な仕上がりになってしまいがちです。こうして金子さんからスタイルやデザインをいただいてつくることで、未経験の事に挑戦でき、さらにファクトリーの技術も上がっていると思います」取材終盤、櫻田氏が語ったこんな言葉が、印象に残った。






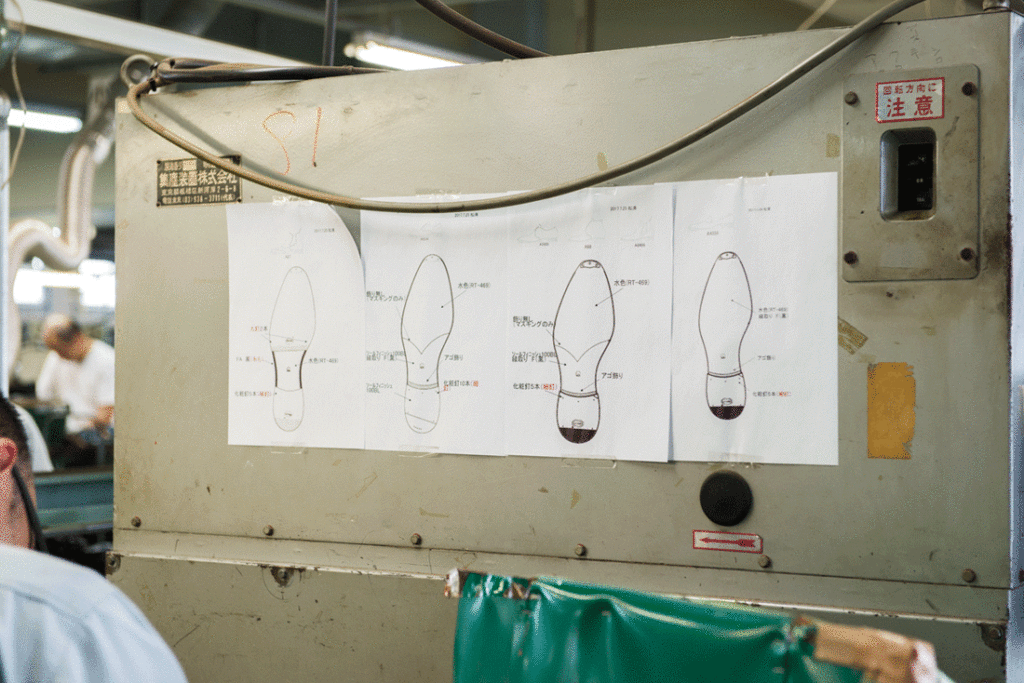
宮城興業のファクトリーへ訪問
『カルマンソロジー』のラバーソールモデルなどが中心
山形県南陽市に、カルマンソロジーの靴づくりを手がけるもうひとつのファクトリー、宮城興業を訪ねた。ここではラバーソールのモデルなどが中心という。ファクトリーのラックには「ヴィブラム コードソール」のブーツが並んでいた。ファクトリー自体はかなり古めかしい、作業場然とした平屋の建物。だがその一方で最新のテクノロジーが導入されている。レザーのクリッキングにはCADと連動した自動裁断機を使用。ノーザンプトンやイタリアなどのファクトリーで導入されているのと同様のものだ。「受注の8割は、型紙や抜き型をつくらずこの自動裁断機を使います。多品種小ロットのオーダーに応え、なおかつ外部に頼らず内製を進めることができます」このように説明するのは、宮城興業の皆川真吾氏。
テクノロジーはマスプロダクションを意味するものでなく、より多彩な靴を手がけるための手段なのだ。そして多彩さの実現はボトムメイキングの現場で、また違った形で表れていた。「木型の形状にあわせた調整や下準備を、作業従事者がその都度できることがうちの強みです。1ラックごとに違う木型があるような現場なので、あらかじめ機械の設定などをするより、各作業者自身が調整する方が早いのです」
つまり、現場の高いスキルや技術力ゆえに、各種のオーダーに対応できているわけだ。このことはカルマンソロジーで展開されている、多様な仕様やディテールを実現するのにも貢献している。工程の終盤、ダブルウェルトのモデルのフィニッシングを見ることができた。デンマーク原皮のキップを国内のタンナーが鞣した革は、銀面(表面)を軽く擦った後に、ワックスとロウを入れて仕上げてある。「こうした革なので、フィニッシングでかなり変化します」と金子氏。ビーワックス入りのクリームを塗り、時間をおいて浸透させ、さらに重ね塗り、という工程を繰り返すという。仕上げはクリスタルワックス、という皆川氏の言葉を継いで、金子氏は次のように語った。「さらにその後、納品されたすべての靴を僕が磨きます。それが最後の 仕上げです」今回最も驚かされた、カルマンソロジーの背後にあるクラフツマンシップの一例だった。
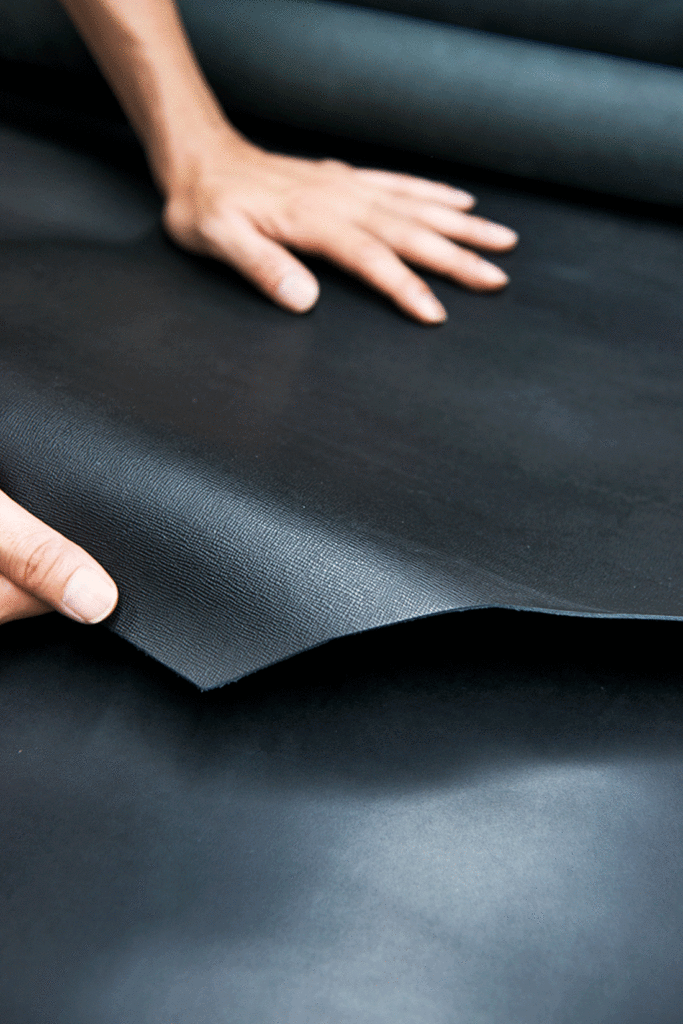







『カルマンソロジー』の由来
2018年よりスタートした、デザイナー金子真氏のメンズシューズブランド。その名はCALM(静寂)とANTHOLOGY (詩集)を合わせた造語で、「言葉なき詩集」という意があるという。「伝統と進化」をコンセプトに、日本人ならではのバランス感覚を備えたスタンダードを目指している。
photographs_Satoko Imazu
〇 雑誌『LAST』 issue.15 より