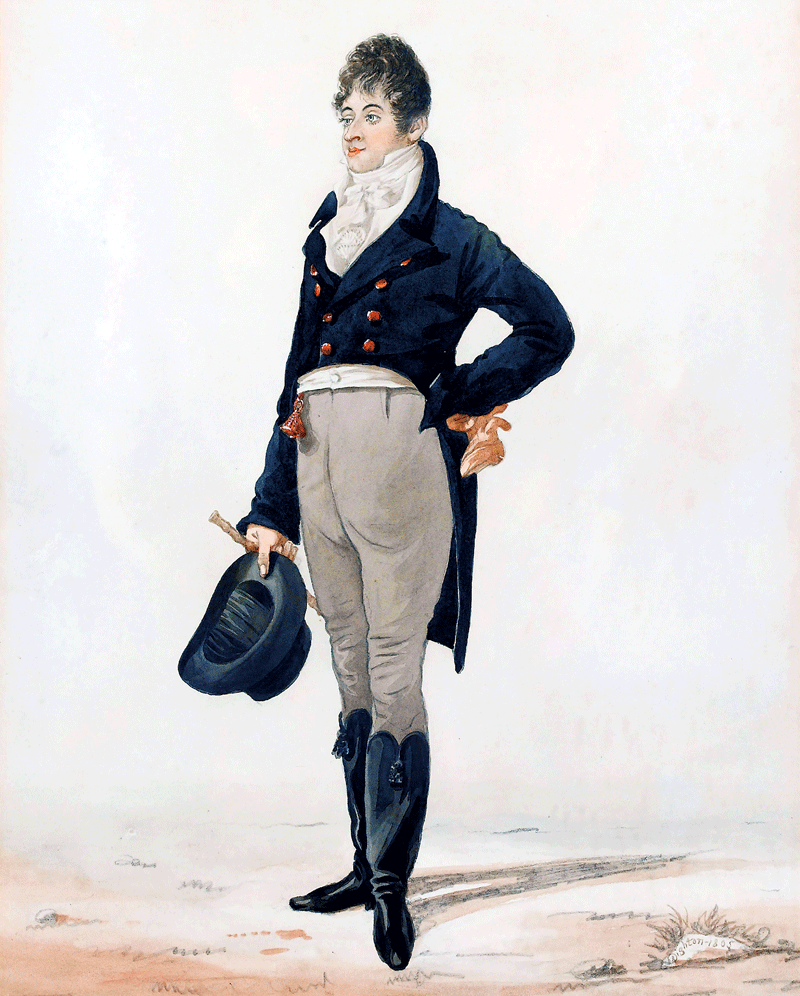
服飾評論家が分析する、「黒の靴」の理由。
かしこまった場の足元は黒革のキャップトウ……確かにシンプルな一文字ステッチの黒い靴はそのような場に向いているように感じるが、何故、そしていつから靴は黒が「品格がある」ことになったのだろう?
“黒”の印象の歴史
この謎を解くには黒なる色のイメージの歴史から考察する必要がある。いずれの色もプラスとマイナス双方の性格を持つが、黒では前者は強さ・超越、後者は恐れ・闇等で、双方の意味が古くから交錯しつつ用いられていた。
例えば喪服は古代ローマで既に黒だったし、主要な聖職者の法衣も11世紀前後からは黒が主流。いずれも「自然を超越した畏敬の象徴」としての選択だったのだろう。黒に匿名性=特定不可能で「混じる」役割を与え、民衆の本音や意思を語らせた点では、13世紀に欧州各地で伝わった「黒騎士伝説」にも注目したい。一方で同時期、黒は「知識や才能の象徴」にもなる。欧米の裁判官や大学の卒業式でお馴染みの黒いローブ姿。これは聖職者の装いを真似て当時登場したものだ。
とはいえ黒が「品格の高い色」という地位を得たのはフランス革命前後とみていい。絶対王政下では名も無き民衆の象徴だった黒が、革命を機に「主役の色」として一気に成り上がったのだ。その立役者がボウ・ブランメル。中産階級出身ながら英国社交界の頂点に達した彼の装いは、前時代の貴族とは対照的な地味な色のものばかり。特に靴は黒のブーツを愛用し、それらをフォロワーが真似た結果、色彩の意識にも革命が起きた。男性の礼装の色として、黒に凛々しい印象が加わったのである。
次のステップは19世紀中盤。欧米で警官のような現業系公職の制服・制靴に、黒が採用され始めたことだ。為政者への個人的感情に関わらず、あくまで国民国家の構成員として、彼らに「職務」なる新たな匿名性を確保しつつ近代国家も体現する。黒の服や靴は単に汚れが目立ちにくい以上に、そうした「個々が混じり平準化した集団」の総意・協調・緩衝の象徴にもなった。
決定打は英国のヴィクトリア女王か。彼女はモード面でも大きな影響を及ぼし、例えば白いウェディングドレスは彼女がアルバート公との婚礼で着たのが始まり。一方彼が没して以降は、長く喪に服し専ら黒い装い。彼女の行動を通じ黒は日常を超越する「厳粛」「哀悼」の色だと世間に改めて示され、前述の凛々しさや集団性とも融合し、黒は遂に品格、つまり「フォーマルでオフィシャルな色」との強固な共通認識を獲得する。
19世紀の技術が導いた黒靴の隆盛
靴周辺の技術的進化と黒との関係をたどっても、「フォーマル化・オフィシャル化」は19世紀の発明が果たした役割が大きい。例えばエナメル。1818年に米国で開発された当初は、防水性が好まれ専ら労働者用の靴のアッパー向け。しかし光沢が永続し婦人のドレスの裾も汚さない点が評価され、やがて礼装向けへと用途が大逆転する。黒の燕尾服が男性の正礼装に昇格する時期とこれが重なり、足元も黒一択となる。
1856年に英国で登場したアニリンに始まる合成染料の普及も一役買った。発色が改善されたことで、黒は傷やダメージを隠しやすく革の安価な大量生産に適する色として、その恩恵を最も授かることになる。前述の公職向け、そしてその頃から激増するビジネスマン向けの靴の需要には、これで応えることになる。
1858年にドイツで発明された、クロム鞣しも重要だ。従来の植物タンニン鞣しより大量の革を短時間に低コストで、しかもよりキメ細かな革をつくれるようにもなった。靴用の「黒のボックスカーフ」は、このお陰で安定生産が可能になったのだ。
文化的・技術的要素が交錯した結果与えられた「黒い革靴の品格」
以上、黒い革靴の品格は、背景こそ古に遡れるものの、直接的起源は決して遠い過去にあるものではない。しかも様々な文化的・技術的要素が交錯した結果、今日的な市民社会の中で相応の価値が与えられたものだ。だからこそ「同調的存在」として、軽装化が進む今日でも依然、共通の足場を築き続けているのだろう。
text_Takahiro lino
〇 雑誌『LAST』 issue.20 より





