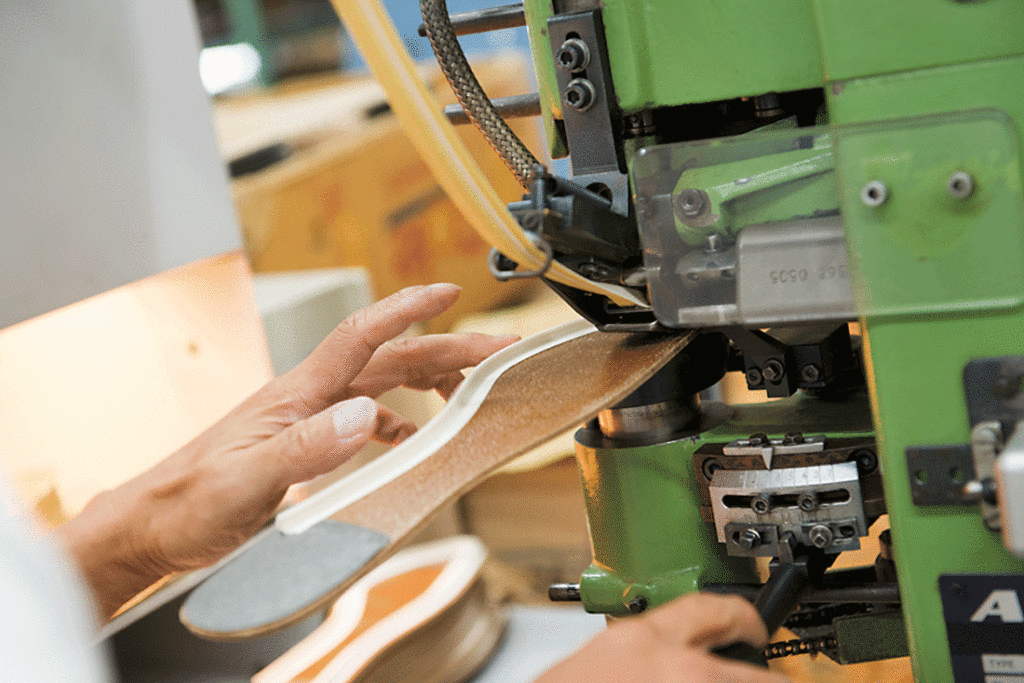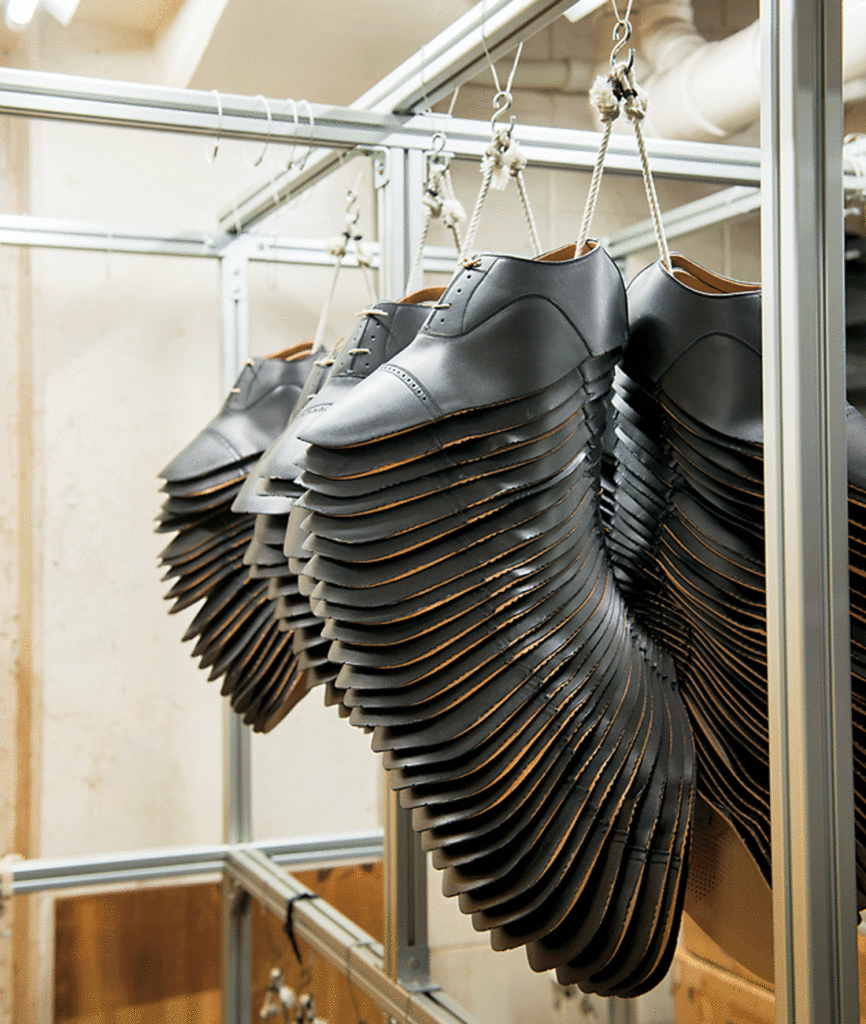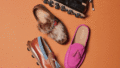グッドイヤーウェルト製法を採用した紳士靴として、いまや日本を代表する存在であるシューズブランド『スコッチグレイン』。同ブランドを手がけるヒロカワ製靴は1964年に台東区で創業し、1978年よりオリジナルブランドとして『スコッチグレイン』をスタート。1979年には隅田川を挟んで対岸エリアの墨田区に本社を移し、以来今日まで同地にて靴づくりを行ってきた。
海外に生産拠点を移すメーカーなども数多い中、一貫して自社による靴づくりを続けてきたヒロカワ製靴と『スコッチグレイン』。そして、この2021年には本拠である墨田の本社工場の増床・リニューアルを果たし、自社による靴づくりの進化・充実を図っている。従来の建物はそのままに、その奥に新たなビルを新設して増床されたファクトリーでは、革靴の素材である革の加工から、靴の仕上げに至るまで、トータルで行われている。

さまざまなパーツから仕上げまで、自社で一貫した靴づくりを行う東京のメーカー。
廣川雅一社長が最初に案内したのは、新しい建物の地下。革底の原材料であるベンズ(底材の革)が積み上げられていた。「この地下のフロアをつくることで、これまで離れた倉庫より持ってきていたベンズなどをストックすることができて、靴づくりの作業効率が格段に上がりました」(廣川社長)またこの地下にはウェルト革などの各種部材も保管されている。ベンズ、ウェルト、そしてグッドイヤーウェルテッドの要であるリブは、『スコッチグレイン』の場合イタリア製が中心になりつつあるという。
「リブは長年付き合いのあったイタリアのウェルトのサプライヤーから紹介されて、イタリア製を使うようになりました。アメリカ製やポルトガル製なども試しましたが、イタリアのリブは織り方がしっかりしていて、〝寝ない〞のです」こうした廣川社長の言葉からは、素材選びの段階から『スコッチグレイン』独自の見識があることが窺える。







次に案内されたのは、新社屋1階の本底や中底の加工を行うエリア。『スコッチグレイン』では本底や中底、さらには靴の踵部分に配する「ハチマキ」などの部材を、先述のベンズから自社で加工している。取材時は中底にリブを貼る作業も行われていた。「土踏まず部分を細く、限界まで攻めたリブ形状にできるのも、自社でつくっているからだと思います」(廣川社長)
旧社屋の1階はアッパー(甲革)の裁断。ここで裁断された革は、山形や秋田の協力工場に送って製甲(縫製)し、このファクトリーに戻ってくる。ちょうど同ブランド人気の姫路・山陽製の撥水レザーを、スタッフが抜き型を使って裁断していた。「コンピュータ制御の自動裁断機を導入しているところも多いですが、革表面の細かな傷などは十分チェックできない。ここはまだ人の目が重要です」と廣川社長。さらにキャップ部のパーツなどは、ひとつひとつ機械で伸ばして傷やピンホールを確認していた。