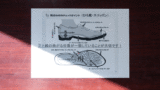「ニューノーマル」などといった言葉とともに、以前とは異なる価値観や感覚で生活することが求められる中、装いをめぐる状況も、大きく変わっている。
例えばリモートワークの恒常化は、それまで徐々に進んできたビジネススタイルのカジュアル化を、一気に進めてしまった。それと同時に、装うことの価値とは何か、なぜその装いを選ぶのか。そうした問い直しが、各自の心の裡で巻き起こっているようだ。
自らにとって本質的なものは何かを再考し、選び、または追求する。本質とは必ずしも「実用」だけではない。その何かが存在することを、「必要」と思えるか。かけがえないと感じるか。そして革靴。特に紐靴(レースアップシューズ)が持っている存在感、エレガンス。それは他では代替できない、エッセンシャルなものではないだろうか。

【ESSENTIAL ELEGANCE】「キャップトウオックスフォード」と「プレーンダービー」が必要不可欠であり定番な理由。
ファッション的意味合いが極めて強いアイテムである靴。しかしそのエッセンシャルな(根源的、本質的な)存在意義は
・足を外部環境から保護する。
・快適な歩行をサポートするである。
更には人間の社会的側面まで考察すると、靴とは
・他者との戦いにおいて生き抜く(戦う)
・特定の労働を効率的に行う(働く)
・舞踏などの娯楽を演出する(愉しむ)
・権威の象徴として自己の優位性を示す(従えさせる)
などの役割が、多元的に絡み合い発展して来たものだ。
今日の紳士靴で最もエッセンシャル(ここでは「欠かせない」と訳そう)と見なされているキャップトウオックスフォードとプレーントウダービーも、以下に述べる歴史的推移を経て上記の要素が簡潔かつ説得力を持って凝縮された典型と言える。
オックスフォードとダービーのルーツ

Fred Astaire
現代の目から見ても、十分に華麗で、時にアクロバティック、そしてエレガントな姿を作品の中で発信しつづけているフレッド・アステア。彼の足元にはレースアップの靴が存在感を示していた。スクリーンを動き回る、軽快なオックスフォード。その様子は現代人が忘れてしまった靴本来のポテンシャルを、見せつけているようにも感じる。
まず双方の靴の原点から見ておこう。オックスフォード(内羽根式紐靴)は1853年に英国・ヴィクトリア女王の夫君であるアルバート公が考案したもので、当時は4穴のミドルブーツだったらしい。後述の外羽根式の紐靴に比べ調節性には若干劣るものの、見た目の華やかさ・格調の高さから、以後パンプスなどに代わり正装・礼装向けの靴として普及し始めた。
一方、ダービー(外羽根式紐靴)の原型を考案したのは、1815年のワーテルローの戦いでプロシア軍を率いたブリュッヒャー元帥。着脱とフィット感の調節が容易な点が、一刻を争う戦闘靴の要素として理に叶っており、この戦争に共に勝利した英国では1820年代以降、まだミドルブーツ丈ではあったが、狩猟靴などのワークブーツを手始めにこのスタイルが急速に普及してゆく。
前者は「従えさせる」立場から、後者は「戦う・働く」の要素が濃い、対照的なルーツである。
当時は西欧社会がまさに産業革命の恩恵を受けていた時代であり、もちろん双方の靴の登場や進化にも影響を与えた。着用感の微調節に不可欠な「鳩目」の金属補強然り、クロム鞣しの革やミシンによる底付け然り。
中でもキャップトウオックスフォードとプレーントウダービーのエッセンシャル性にプラスに働いたのは19世紀期〜後半、製図の進化による左右別々の靴の再登場と、それとほぼ同時期の「先芯=トウキャップの導入」かもしれない。左右別々の形状を維持するのが当初の目的だった先芯は、つま先の補強・保護も兼ねるようになり、1880年代には「デザイン」としての要素も帯びるようになる。先芯の存在感を全くアッパーの表面に見せないもの、表にこそ見せないが封入する際の目安線は残したもの、敢えて外に露出させた分厚いもの…… その違いこそ今日のキャップトウとプレーントウの違いそのものであり、いわば紳士靴のバリエーションの原点となったからだ。
キャップトウオックスフォードとプレーンダービーの歴史的推移。工業化・近代化の中で靴の本質は磨かれた。
他方、両者がエッセンシャル性を獲得できた理由を考察するには、「ブーツ(長靴)からシューズ(短靴)へ」という19世紀後半から20世紀初頭にかけての靴自体の変化にも着目する必要がある。これは当時の生活や社会変化の結果であり、ゆえに服装の変化をまず語らねばなるまい。
フランス革命以前は労働者階級の象徴だったくるぶし丈で裾幅に余裕のあるトラウザーズが、19世紀以降他の階級にも浸透し、その末期には従来の服より圧倒的に楽で簡素なことから台頭してきた「スーツ」のボトムズとして、ドレスウェア・ビジネスウェアとしての地位を確立する。くるぶしをホールドしない分、楽な履き心地のシューズの地位も同時に向上し、中でもキャップトウオックスフォードとプレーントウダービーは、シンプルなデザイン故に当時のスーツ姿の足下に最適とみなされ支持を広げ、以後それが完全に定着することになる。
次に交通インフラの進化=馬・馬車から鉄道そして自動車への変化。乗馬機会の激減に伴い、丈の長い乗馬ブーツは無用の長物になった。また、自動車の普及は道路の舗装化も促進し、処理しきれないゴミや汚物を道路上に放置していたそれ以前の習慣も改めるべく、下水道の整備も積極的に行われた結果、丈の短いシューズのような防汚機能の多少劣る靴でも平気で履ける場所が格段に増えることに繋がった。特に清潔感を感じさせるデザインのキャップトウオックスフォードとプレーントウダービーには、「快適な都市生活の象徴」としての意味合いも自然に付加され、シューズの中でも一段上の印象を得ることになったのは容易に想像がつく。
さらに、生産効率面での優位性も挙げられるだろう。ブーツとシューズを比べると、その容積から見ても、同量の原材料かつ同一の時間でどちらが多く製造できるかは言わずもがなだ。そして生産効率は機能最大限・費用最小限が常に至上命題となる軍務用の「オフィサーシューズ」や警官・郵便配達員・鉄道員など向けの「サービスシューズ」では最重要事項でもある。アッパーを構成するパーツや縫合線が少なくて済むキャップトウオックスフォードとプレーントウダービーが、シューズの台頭以降これらに極めて高頻度に採用されて来たのは、よって至極当然なのである。
更には、現代とは異なり20世紀中盤までは相次ぐ戦争の影響で、主要国では軍務に携わった経験のある人の割合が今日よりも多かった点も、何気にこれらの靴のエッセンシャル性獲得に繋がったのではないか。「公務」の記憶が残っているからこそ、退役後も無難さ重視で同種の靴を選んでしまう心理には納得がいくだろう。
必要不可欠な靴の要件とは。
総括すると、キャップトウオックスフォード並びにプレーントウダービーは、
A . 数多くの「現場」で鍛え抜かれている。
B . その結果、様々な服や場面に合わせやすい。
C . 構造的にも必要十分で理に叶っている。
という3つの要件のもとに成立していた存在だからこそ、エッセンシャルな靴たり得たのである。
近年は労働環境やライフスタイルの変化に伴い、紳士靴そのものの存在意義が薄れ始めているのは事実だ。紳士靴そして革靴の未来は、双方のスタイルが備えるこうした要件を、つくる側も履く側もどう認識し直すかが重要なのかもしれない。
語り手:いいのたかひろ
企業勤務を経て2002年より服飾ジャーナリストとして活動。 紳士靴に限らず、男性の服飾品全般に関して執筆している。著書に『紳士靴を嗜む はじめの一歩から極めるまで』(朝日新聞出版)ほか。
text_Takahiro Iino, photograph_Toru Oshima
〇 LAST issue19 より